リラクゼーション腸活®とは?
様々な腸活がある中
当協会は「腸脳相関」に着目
(腸脳相関を通じて、心の安定と健康を実現します)
私たちの体にとって「腸」は、ただの消化器官ではありません。セロトニン(別名:幸せホルモン)の約95%は腸で生成されており、腸のぜん動運動や血流の調整、骨形成、免疫機能の維持など、全身の健康に大きく関わっています。
一方、脳で生成される残りの5%のセロトニンは、気分を安定させたり、穏やかな感情を保ち、良質な睡眠を促す働きを担っています。脳内セロトニンを合成するために必要なアミノ酸「トリプトファン」は、腸から吸収されて脳に運ばれるため、腸内環境の健全性がメンタルの安定にも直結していると言えるのです。
このように、腸と脳は互いに密接に影響を与え合う関係にあり、これは「腸脳相関」として知られています。
この腸脳相関に対して直接アプローチできるのが、私たちが提供するリラクゼーション腸活という施術です。施術によって副交感神経が優位になると、腸のぜん動運動が活性化され、セロトニンの分泌も促進されます。また、腸には体内の免疫細胞の約70%が集中しているため、腸の働きが整うことは免疫力の向上や体調管理の基盤づくりにもつながります。
つまり、リラクゼーション腸活は、「腸」「脳」「自律神経」「免疫」を同時に整える、現代人の心身を支える統合的なアプローチ方法なのです。
ストレスの多い現代社会において、外からではなく内側から整えるこの実践的な方法が、健やかな暮らしの鍵となります。
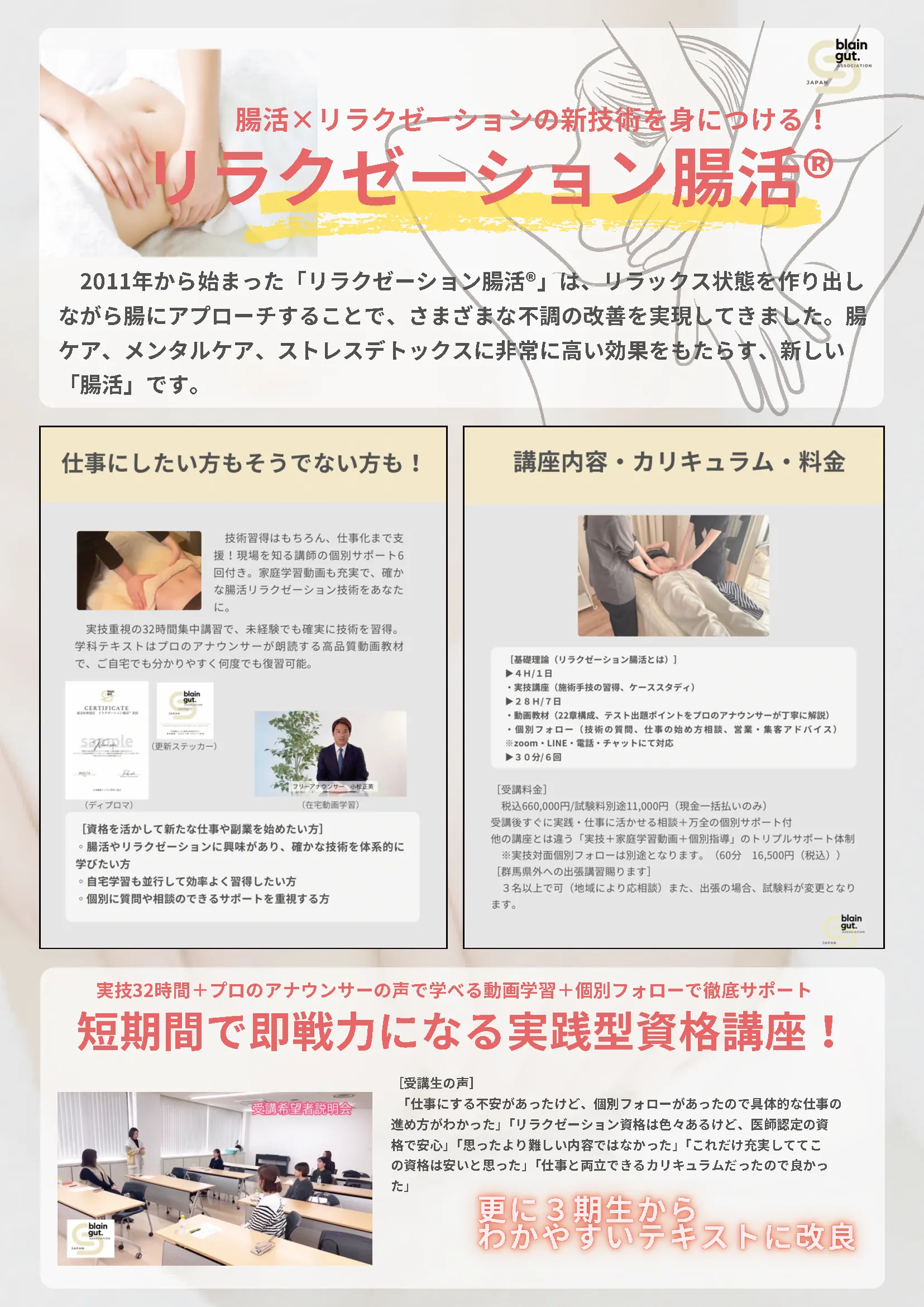
現在の腸活需要
顧客ニーズと市場の動向
【市場の動向】

新型コロナウイルス感染症の流行以降、産業医への相談件数は「株式会社メンタルヘルステクノロジーズの産業医のコロナ前後の変化に対する調査」では、「120%~150%増」と答えた産業医は6割を超えており、相談内容は「感染症予防・テレワークに関する相談」「ストレスに関する相談」が上位にきています。腸内細菌のバランスがよくなると、健康の維持や向上につながることは、最近の多くのテレビや雑誌に取り上げられ、認識されるようになりました。脳がストレスを感じると腸内環境は乱れ、その腸内環境の乱れが更に不安やストレスを生むという悪循環になってしまいます。この悪循環を好循環に変えるためには、乱れを生みにくい健やかな腸内環境を作ることが一助になると考えられています。腸内環境と免疫に密接につながっていることが分かったことから市場は今後も拡大すると見込まれています。
【顧客ニーズ】

雑誌「オレンジページ」での調査によると、腸内環境を整えたいと考えている人は93.3%おり、また腸内環境に自信のない人も約7割いるものの、その中で実際に腸活をしたことがある人は35%です。加えてビオフェルミン製薬が行った「腸活に関する意識調査」によると、64.8%の人が腸活は「継続することが大事」であると考えていますがなかなか継続できないのが課題です。こうした調査からも忙しい現代においては習慣的に腸活を生活に取り入れることに大きな課題があります。
「リラクゼーション腸活」は日々の生活で無理なく腸活を実現するためのリラクゼーションマッサージでの健康維持をする腸活方法です。現在、医師、医療従事者もリラクゼーション腸活を定期的に受けております。また病院の一角でリラクゼーション腸活を取り入れたいとご希望される医師もいらっしゃいます。
現役アナウンサーも
リラクゼーション腸活を推薦!
フリーアナウンサー 小松 正英
(元群馬テレビアナウンサー/現在はフリーアナウンサーとして海外サッカー、Jリーグ、DAZNなどで実況中継)


協力病院
協力病院医師からのコメント
前橋善衆会病院
榛東わかばクリニック
院長 中沢 克彦医師
腸活について
最近、マスコミ等々で「腸活」という言葉をよく耳にします。 「腸活」とは何でしょう? 「腸活」とは「腸内フローラ」を整えることです。ヒトの腸の中には数万種類、1000 兆個以上という とてつもない数の腸内細菌が棲んでおり、その重さは 1-2Kg にも及びます。ヒトの身体全体の細胞が約 60 兆個ですから腸内細菌の数たるや天文学的な数です。その腸内細菌は菌の種類ごとにかたまって腸の壁にびっしり張り付いており、顕微鏡で見るとお花畑(flora)のように見えることから「腸内フローラ」(正式には腸内細菌叢)と呼ばれるようになりました。
この腸内フローラのうち菌種が判明しているのはごく一部で、大部分は実はわかっていません。これからの大きな研究課題です。
腸は体内の免疫システムの多くを支配しており、脳の指令と関わりなくむしろ腸が脳を支配する部分もあり、『腸は第二の脳』とも呼ばれます。そんな大切な腸内の環境を良くしておく事が健康維持にとても大切なことは言うまでもありません。腸内細菌は善玉菌、悪玉菌、日和見菌(ひよりみきん)の 3 種類に分けられます。日和見菌とはその場の腸内環境で善玉菌の味方をしたり悪玉菌の味方をしたりするコウモリのような菌です。具体的には善玉菌はビフィズス菌、乳酸菌など。悪玉菌はブドウ球菌、大腸菌(有毒性)、ウェルシュ菌など。日和見菌は大腸菌(無毒性)、連鎖球菌、バクテロイデスなどです。善玉菌:悪玉菌:日和見菌の割合は約 2 割:1 割:7 割が理想的とされ、割合が崩れると体調不良を起こします。悪玉菌にもそれなりの役割があり、ゼロではいけません。我々の腸内細菌は日々、時々刻々と善玉菌と悪玉菌がせめぎ合って縄張り争いをしています。
それを司るのは自律神経です。自律神経には交感神経(緊張したりストレスがある時に働く神経)と副交感神経(ゆったりリラックスしている時に働く神経)があり、常にバランスをとっています。この自律神経のバランスが崩れると腸内環境も悪くなり、結果として免疫力も低下し様々な病気の原因にもなります。
「腸活」にはバランスのとれた食生活、適度な運動、それに自律神経を整える生活が大切です。健康な生活を送るためにぜひ「腸活」を念頭においてみて下さい。
市川クリニック
院長 市川 翔医師
精神と腸活
精神科で診療を行っていると、下痢や便秘、腹痛など腸のトラブルを抱えている人が多くみられます。腸のトラブルが先行し、精神症状が出現することも少なくありません。
最近ではメディアなどで「しあわせホルモン」という名前で紹介されることが多いのですが、その正体は「セロトニン」という脳内のホルモンです。セロトニンは精神を安定させてくれる作用があります。脳はストレスや緊張を感じるとセロトニンを出し、自律神経のバランスを取ろうとし、精神を安定させようとします。そのため、セロトニンが不足すると疲労やイライラ、意欲低下、不眠といった症状が出ることがあります。
セロトニンは脳内だけでなく、腸内でも合成されます。実際、体内のセロトニンの大部分は腸内で生産されています。腸内フローラのバランスが崩れると、腸内でのセロトニンの合成が低下する場合があり、これが脳のセロトニンレベルに間接的に影響を及ぼし、気分の落ち込みを引き起こす可能性があります。
医学的にも「脳腸相関」というのがあり、以前から脳と腸は深く関わっていると言われてきました。最近では腸内フローラと精神に関する研究が増えています。脳が不調をきたすと腸内の環境が乱れやすく、腸内の環境が乱れると不安やストレスを産むことが最近の研究で分かってきています。
また、セロトニンはその材料として必須アミノ酸の「トリプトファン」が必要となります。ただし、トリプトファンは体内で生成できないので、食事から摂らなければなりません。
トリプトファンが多く含まれている食材は主に、大豆製品や乳製品などがあります。また、それらの食品と「ビタミンB6」や「炭水化物」を一緒に摂取するとトリプトファンが作られやすくなると言われています。ビタミンB6は、にんにくやまぐろ、レバーなどに多く含まれています。
腸を整えることにより精神的な安定効果も期待できる可能性があると考えています